 |
|
 |
|
| 現在、「すし」といえば、大体にぎりずしのことです。生の魚とすし飯を組み合わせたにぎりずしは、日本特有の食べ物です。それが今では、健康食として世界的に知られ、アメリカをはじめとして海外でも人気が高くなっています。「すし」は、特別な日に食べる郷土料理として発達し、押しずし、巻ずし、ちらしずしなど、その土地ならではの材料を使ったさまざまな「すし」があります。 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
| すしのおいしさは、すし飯に左右されるんだ。そのたき方や味の加減を“しゃり加減”といい、ごはんたきは、しゃり屋とよばれる職人の仕事だったんだよ。合わせずの作り方は地方によってかなりちがい、例えば、東京風のすし(江戸前ずし)はあまみが少なく、関西ずしはあま口なんだ。ふつう、いなりずしなどの冷めてから食べるすしは、すし飯がバラバラにならないよう砂糖を使うんだよ。 | 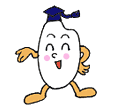 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
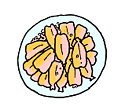

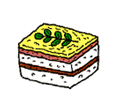
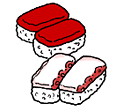
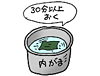 (1)米3カップを洗い、水3〜3 1/3カップの水にこんぶ(10 cmぐらい)も入れて、30分以上吸水させる。
(1)米3カップを洗い、水3〜3 1/3カップの水にこんぶ(10 cmぐらい)も入れて、30分以上吸水させる。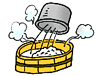 (2)ごはんをたく。スイッチが切れたら、10分ほどむらし、炊飯器からすしおけにごはんを一気に移す。
(2)ごはんをたく。スイッチが切れたら、10分ほどむらし、炊飯器からすしおけにごはんを一気に移す。 (3)ごはんが熱いうちに、合わせずをふりかけ、少しむらす。
(3)ごはんが熱いうちに、合わせずをふりかけ、少しむらす。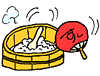 (4)木しゃもじですし飯を切るように混ぜながら、うちわか扇風機で手早く冷まし、ごはんにすの味をなじませる。
(4)木しゃもじですし飯を切るように混ぜながら、うちわか扇風機で手早く冷まし、ごはんにすの味をなじませる。